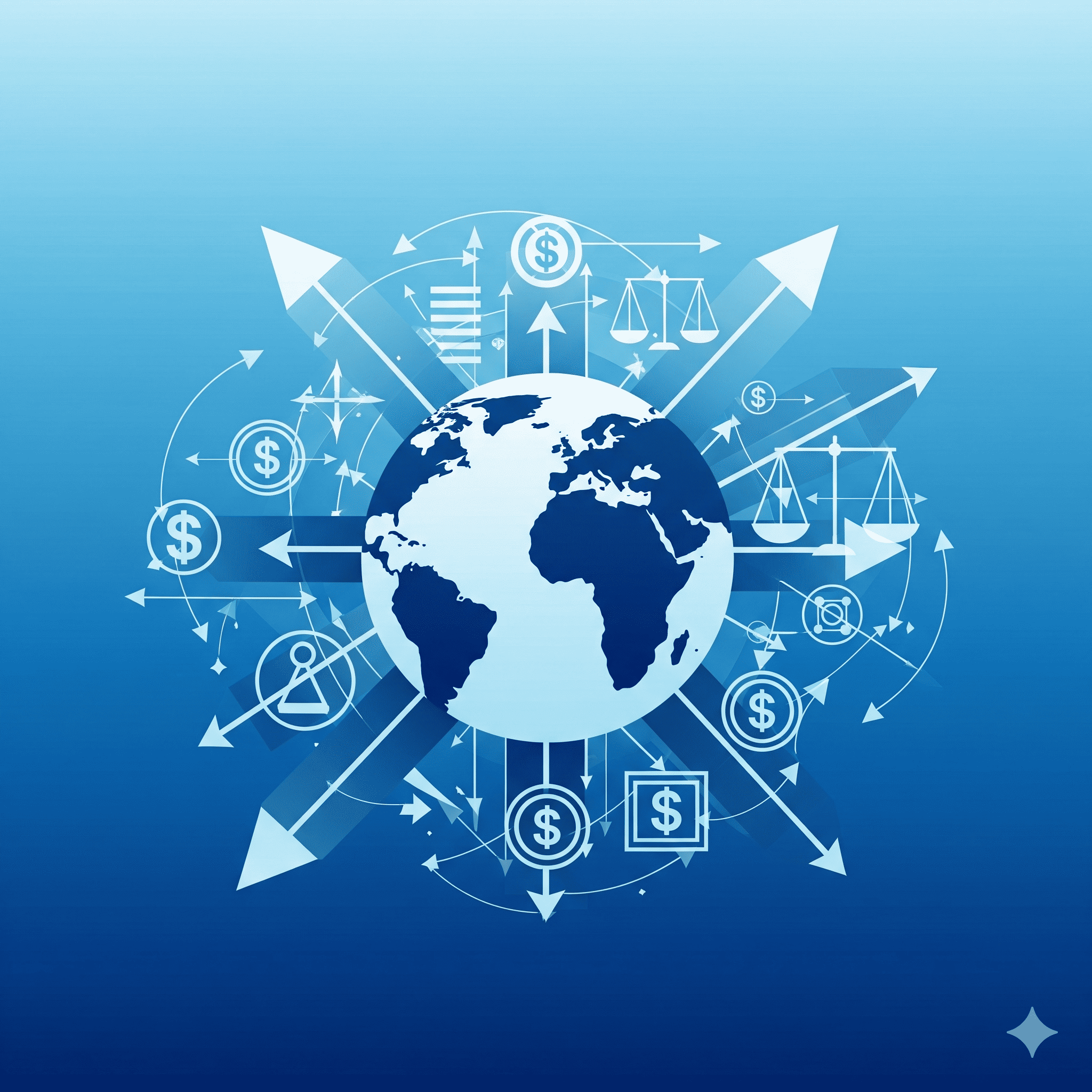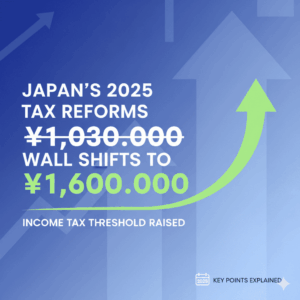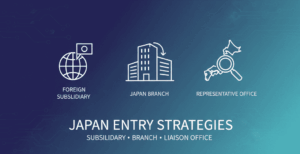納税義務者の4つの区分と課税範囲
日本の税制では、納税義務者を4つの区分に分けて、それぞれ異なる課税範囲を設定しています。
居住者とは、国内に住所を有する個人、または現在まで引き続いて国内に1年以上居所を有する個人のことです。居住者は、原則として国内外すべての所得について日本で課税されます。
居住者の中でも「非永住者」という特別な区分があります。これは、日本の国籍を有さず、かつ過去10年以内で国内に住所・居所を有していた期間が5年以下の個人のことで、一般の居住者より課税範囲が限定されています。
非居住者とは、国内に住所も1年以上の居所も有しない個人のことです。日本に一時的に滞在している外国人や、海外に移住した日本人などが該当します。非居住者は、原則として国内源泉所得のみが日本での課税対象となります。
内国法人とは、国内に本店または主たる事務所を有する法人のことです。日本で設立された株式会社や有限会社などが典型例です。内国法人は、原則として国内外すべての所得について日本で課税されます。
外国法人とは、国内に本店も主たる事務所も有しない法人のことです。外国で設立された会社が日本で事業活動を行う場合などが該当します。外国法人は、原則として国内源泉所得のみが日本での課税対象となります。
国内源泉所得による課税制限の仕組み
国内源泉所得とは、その所得の発生源泉地が日本国内にある所得のことです。例えば、日本国内の不動産から生じる賃貸収入、日本企業からの配当、日本国内での役務提供に対する対価などがこれに該当します。
なぜ国内源泉所得に限定するのでしょうか。非居住者・外国法人に対して課税権を行使する根拠として、「その所得が日本国内で発生している」という点を重視しているためです。これは国際的に一般的な考え方で、所得の発生地である国が課税権を持つという「源泉地主義」の原則に基づいています。
課税範囲の違いを整理すると以下のようになります。居住者・内国法人については全世界所得課税(国内外すべての所得)が適用され、非居住者・外国法人については国内源泉所得のみ課税となります。
この区分により、日本は自国の居住者・内国法人については包括的に課税し、外国の居住者・法人については限定的に課税するという明確な線引きを行っています。
外国法人の「国内源泉所得」の定義(法人税法第138条一部の内容、抜粋改変あり)
第一号 恒久的施設を通じた事業所得
外国法人が日本に恒久的施設(PE:Permanent Establishment)を設けて事業を行う場合の所得について規定しています。
【重要なポイント】
恒久的施設が外国法人から独立した事業者であると仮定
以下の要素を総合的に勘案して所得を算定:
恒久的施設が果たす機能
恒久的施設で使用する資産
恒久的施設と本店等との間の内部取引
その他の状況
恒久的施設の譲渡により生ずる所得も含む
【本店等の定義】 外国法人の本店、支店、工場その他これらに準ずるもので、恒久的施設以外のものを指します。
第二号 国内資産の運用・保有所得(恒久的施設を有しない外国法人についても課税対象)
国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得が対象ですが、所得税法第161条第1項第8号から第11号まで及び第13号から第16号までに該当するものは除外されます。
【除外される所得の例】
配当等
利子等
使用料等
給与等
第三号 国内資産の譲渡所得(恒久的施設を有しない外国法人についても課税対象)
国内にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるものが対象です。
第四号 人的役務提供事業の対価(恒久的施設を有しない外国法人についても課税対象)
国内において人的役務(人によるサービス)の提供を主たる内容とする事業を行う法人が受ける対価が対象です。対象となる事業は政令で定められます。
第五号 不動産等の貸付け対価(恒久的施設を有しない外国法人についても課税対象)
以下の貸付けによる対価が対象:
不動産関連
国内にある不動産の貸付け
国内にある不動産の上に存する権利の貸付け
採石権の貸付け
地上権の設定
その他不動産等を使用させる一切の行為
鉱業権関連
租鉱権の設定
船舶・航空機関連
日本の居住者又は内国法人に対する船舶若しくは航空機の貸付け
第六号 その他の国内源泉所得(恒久的施設を有しない法人についても課税対象)
前各号に掲げるもののほか、その源泉が国内にある所得として政令で定めるものが対象です。
第2項 内部取引の定義
第1項第一号で言及する「内部取引」について詳細に定義しています。
内部取引とは、外国法人の恒久的施設と本店等との間で行われた次のようなの事実:資産の移転、役務の提供、その他の事実
【判定基準】 独立の事業者の間で同様の事実があったとしたならば、次ような取引が行われたと認められる場合:資産の販売、資産の購入、役務の提供、その他の取引
【除外される取引】
資金の借入れに係る債務の保証
保険契約に係る保険責任についての再保険の引受け
その他これらに類する取引として政令で定めるもの

外国法人の法人税の課税標準(法人税法第141条一部の内容、抜粋、改変等あり)
外国法人に対して課する各事業年度の所得に対する法人税の課税標準(税金計算の基礎となる金額)を定めています。外国法人を「恒久的施設を有するかどうか」で2つに分類し、それぞれ異なる課税方式を採用しています。
第一号 恒久的施設を有する外国法人
【対象】 日本国内に恒久的施設(PE:Permanent Establishment)を設けている外国法人
【課税標準となる国内源泉所得】 以下の2つの区分に分けて規定されています:
イ 第138条第1項第1号の国内源泉所得
【内容】 恒久的施設を通じて事業を行うことにより生ずる所得
【具体例】
日本支店が行う営業活動から生じる利益
恒久的施設に帰属する資産の運用益
恒久的施設と本店との内部取引から生じる所得
恒久的施設自体の譲渡により生ずる所得
ロ 第138条第1項第2号から第6号までの国内源泉所得
【内容】 恒久的施設以外の活動から生じる国内源泉所得(ただし、イに該当するものを除く)
【具体例】
恒久的施設以外が保有する日本国内の不動産からの賃貸収入
恒久的施設以外が行う日本国内の資産譲渡益
恒久的施設以外が日本で提供する人的サービスの対価
その他の国内源泉所得
第二号 恒久的施設を有しない外国法人
【対象】 日本国内に恒久的施設を設けていない外国法人
【課税標準となる国内源泉所得】 第138条第1項第2号から第6号までに掲げる国内源泉所得
【具体例】
日本国内の不動産からの賃貸収入
日本国内の資産の譲渡益
日本国内での人的サービス提供の対価
日本の居住者・内国法人への船舶・航空機の貸付け対価
その他政令で定める国内源泉所得
【注意点】 恒久的施設がないため、第138条第1項第1号(恒久的施設所得)は対象外です。
課税方式の違い
恒久的施設を有する外国法人については、総合主義的課税:恒久的施設所得+その他の国内源泉所得により包括的な課税が行われる
恒久的施設を有しない外国法人については、限定的課税:特定の国内源泉所得のみの限定的な日本との関わりに対応した課税となっている。
外国法人の日本における事業活動の程度に応じて、適切な課税範囲を設定しています:
恒久的施設の有無による区分:日本での事業活動の実質的な程度を反映
所得の二重計上防止:恒久的施設所得とその他の国内源泉所得の適切な区分
国際課税原則との整合:OECD モデル租税条約等の国際基準との調和
この規定により、外国法人は日本での事業展開の形態に応じて、公平かつ適正な税負担を負うことになります。
課税方法の対応関係と実務上の取扱い
非居住者・外国法人の国内源泉所得に対する課税方法は、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つ目は申告納税方式です。これは他の所得と合算して総合的に課税される方式で、納税者自身が確定申告を行う必要があります。
2つ目は源泉分離課税方式です。これは所得の支払時に源泉徴収され、それで課税関係が完結する方式です。
どちらの課税方式が適用されるかは、主に恒久的施設(PE)の有無および国内源泉所得がそのPEに帰属するかどうかによって決まります。恒久的施設があり、所得がPEに帰属する場合は原則として申告納税となり、恒久的施設がない、またはPEに帰属しない所得については原則として源泉分離課税となります。
実務上、源泉分離課税の場合は、支払者(日本の会社など)が所得の支払時に一定の税率で所得税を徴収し、それで課税関係が終了します。一方、申告納税の場合は、非居住者・外国法人が自ら確定申告を行う必要があります。
まとめ
非居住者・外国法人については国内源泉所得に課税範囲を限定し、恒久的施設の有無に応じて適切な課税方法を選択することで、過度な課税を避けつつ、適正な税収確保を図っています。日本への進出を考える外国法人の方は、これらの基本的な仕組みを理解することが重要です。