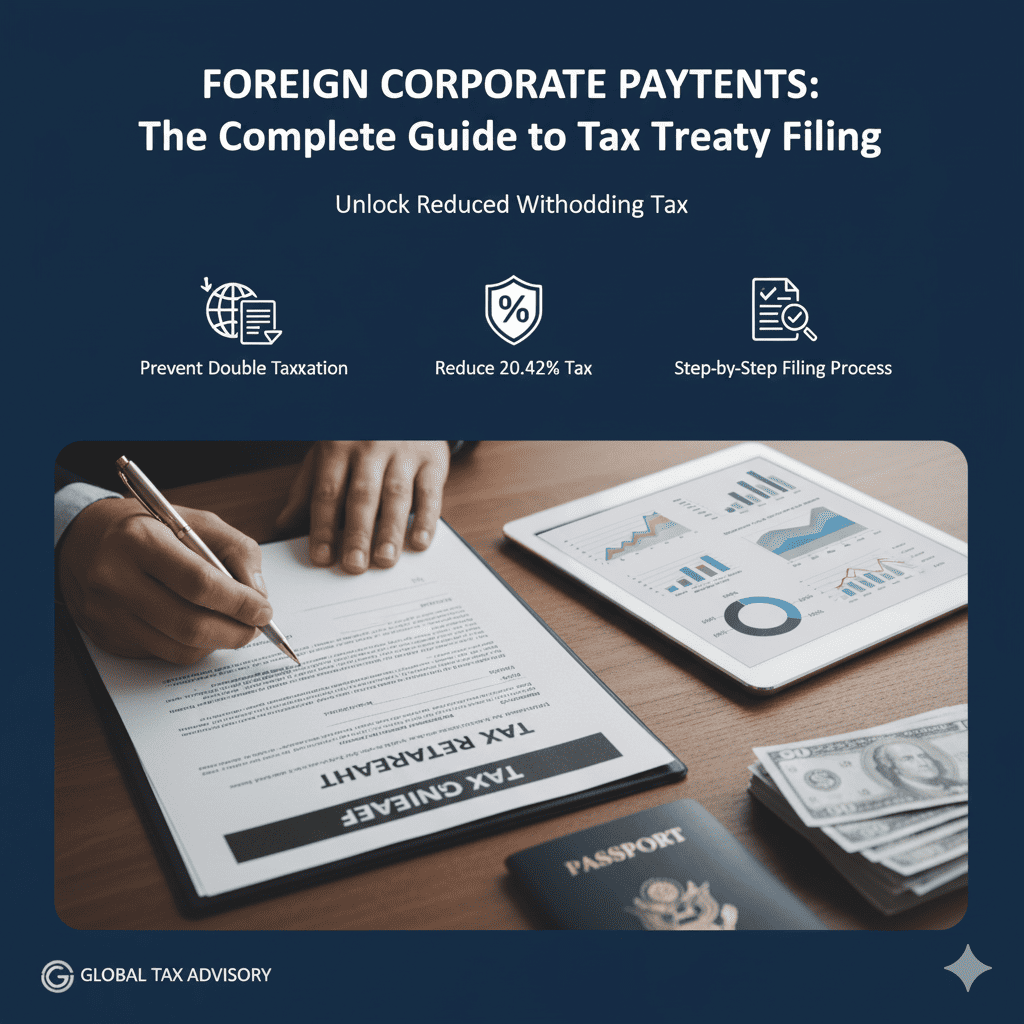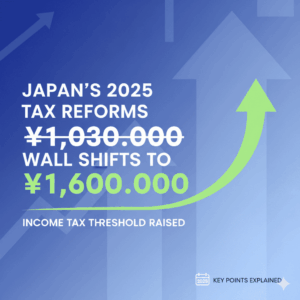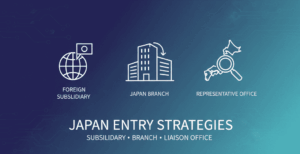外国法人への支払いがある場合
外国法人に配当金や利子、使用料を支払う際、適切な手続きを行わないと20.42%もの高い源泉税が課されてしまいます。租税条約を正しく適用することで、この税率を大幅に軽減、場合によっては完全に免除することが可能です。しかし、手続きを間違えると追徴課税や加算税のリスクが生じるため、正確な知識が不可欠です。
本記事では、租税条約の基本概念から具体的な届出書提出手続きまで、実務担当者が知っておくべき重要なポイントを分かりやすく解説します。
租税条約とは?基本概念を理解する
租税条約とは、国と国の間で締結される国際的な税務に関する取り決めです。最も重要な目的は「国際的な二重課税の防止」にあります。
具体例を見てみましょう。アメリカの会社が日本の会社から配当金を受け取る場合、何も取り決めがなければ日本で源泉税が課され、さらにアメリカでも税金が課される可能性があります。これが二重課税です。租税条約は、このような不合理な二重課税を防ぐために存在します。
日本は現在、アメリカ、イギリス、ドイツ、シンガポール、香港など約70カ国・地域と租税条約を締結しています。各条約の内容は国ごとに異なるため、具体的な軽減税率は個別に確認する必要があります。
租税条約の適用により、通常20.42%の源泉税率が大幅に軽減されます。例えば、日米租税条約では配当の場合5%または10%、利子については完全免除(0%)となります。
源泉徴収制度の基本的な仕組み
源泉徴収とは、所得の支払者が支払時に税金を差し引いて、代わりに国に納税する制度です。外国法人への支払いにおいても、この制度が適用されます。
基本的な流れは以下の通りです。まず、日本の会社(支払者)が外国法人(受領者)に所得を支払います。その際、支払者が所得から税金を差し引き(源泉徴収)、差し引いた税金を税務署に納付します。
源泉徴収の対象となる主な所得には、配当金(株式の配当)、利子(貸付金の利息、債券の利子)、使用料(特許権、商標権、著作権の使用料)、役務提供報酬(技術指導料、コンサルティング料など)があります。
租税条約を適用しない場合、これらの所得には原則として20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)の源泉税が課されます。
租税条約適用のための届出書提出手続き
租税条約の軽減・免除を受けるためには、事前に「租税条約に関する届出書」を提出する必要があります。この手続きは、日本側の支払者(源泉徴収義務者)が中心となって行います。
届出書は支払内容によって様式が異なります。主なものには、配当に対する軽減・免除(様式1)、利子に対する軽減・免除(様式2)、使用料に対する軽減・免除(様式3)があります。外国法人は、支払者ごとに届出書を作成し、最初の支払を受ける日の前日までに、支払者を経由して支払者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
相手国によっては、必要な添付書類として、相手国の税務当局が発行する「居住者証明書」があります。これは、受領者がその国の税務上の居住者であることを証明する重要な書類で、発行日から1年以内のものを使用する必要があります。
令和3年4月以降、一定の要件を満たす場合には、これらの書類を電磁的方法(PDF形式のイメージデータなど)で提供することも可能になりました。これにより、手続きの効率化が図られています。
実質的受益者の概念と重要な注意点
租税条約適用において最も重要かつ複雑な概念の一つが「実質的受益者」(Beneficial Owner)です。これは、単に法的に所得を受け取る権利を持つだけでなく、経済的に真に利益を享受する者でなければならないという考え方です。実質的受益者とは、租税条約上の軽減税率や免税の恩恵を受けられる「真の受益者」 を指します。単に名義上の受取人ではなく、経済的に所得を享受し、使用・処分する権限を有する者 を意味します。
実質的受益者に該当しない例として、代理人や受託者(他人のために所得を管理しているだけの場合)、導管会社(所得を単に通過させるだけの中継機能しか持たない会社)、ペーパーカンパニー(実質的な事業活動を行っていない会社)があります。
判定のポイントには、所得に対する処分権があるか、実質的な事業活動を行っているか、受け取った所得の大部分を第三国の者に支払う義務があるか、十分な実体(人員、設備、資金)があるかなどがあります。
特典条項を有する租税条約の場合は、さらに厳格な要件があります。特典条項の適用対象となる所得について軽減・免除を受ける場合には、届出書のほかに「特典条項に関する付表(様式17)」および「居住者証明書」の提出が必要になります。
手続きを怠った場合のリスクと対応策
適切な手続きを行わずに租税条約の適用を受けようとした場合、または手続きに不備があった場合、深刻なリスクが生じる可能性があります。
主なリスクとして、追徴課税が挙げられます。届出書の提出を怠ったり、不適切な軽減税率を適用した場合、法定税率(20.42%)と軽減税率の差額について追徴課税される可能性があります。
さらに、各種加算税が課される場合があります。過少申告加算税(10%または15%)、無申告加算税(15%または20%)、重加算税(35%または40%、隠蔽・仮装があった場合)などです。納付が遅れた期間に応じて延滞税も課されます。
ただし、救済措置も用意されています。事前に届出書を提出できなかった場合でも、後日「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書(様式11)」を提出することで、軽減または免除の適用を受けた場合の源泉徴収税額と国内法による税率で徴収された税額との差額について還付を請求することができます。
リスク回避のためには、事前の十分な準備と確認、専門家への相談、疑義がある場合の事前照会、適切な書類保管が重要です。
まとめ
租税条約の適用は、外国法人との取引において大幅な税負担軽減をもたらす重要な制度です。しかし、その恩恵を受けるためには、正確な知識と適切な手続きが不可欠です。
特に重要なのは、事前の届出書提出、実質的受益者要件の確認、必要書類の適切な準備です。手続きを怠った場合のリスクは大きいものの、救済措置も用意されているため、適切な対応により問題を解決することができます。国際取引が増加する現代において、租税条約の知識は企業の税務戦略上極めて重要な要素となっています。